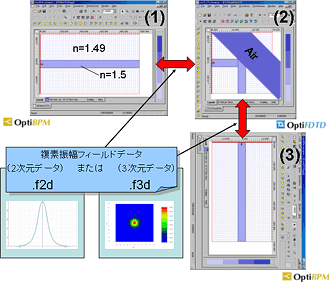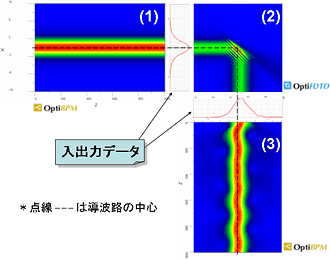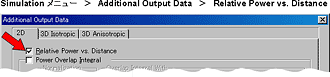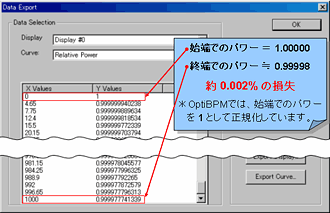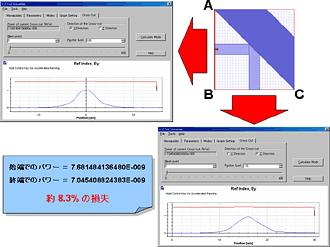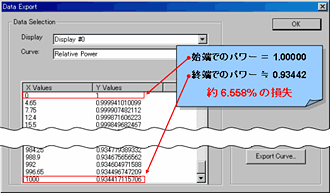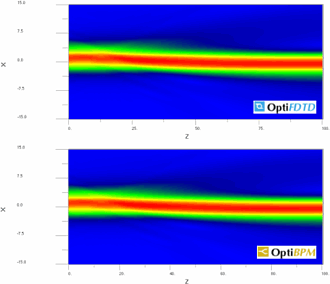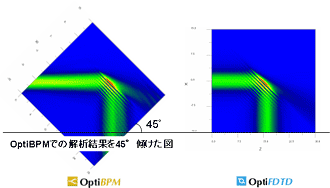OptiBPM>OptiBPMとOptiFDTD を用いた連携解析例
OptiBPMとOptiFDTD を用いた連携解析例
(1) はじめに
光デバイスの設計や解析を行うツールには、対象とするデバイスの種類や物理現象、内部で使用しているアルゴリズムに応じて非常にたくさんのソフトウェアが存在します。近年、光デバイスの多用化にともない、複数のソフトウェアを連携させてデバイス全体の解析を行なう必要性が高まりつつあります。ここでは、ビーム伝搬法(BPM法)を用いた導波路解析ソフトウェアOptiBPM とその姉妹品となる有限差分時間領域法(FDTD法)を用いた時間領域光伝搬ソルバOptiFDTD を連携させ、90°反射のあるモデルを解析した例をご紹介します。
(2) OptiBPM とOptiFDTD 間のデータ受け渡し
OptiBPM とOptiFDTDでは、お互いの複素振幅フィールドデータの受け渡しが可能です。OptiBPMではBPM法で導波路の伝搬シミュレーションを行ない、結果をテキストファイルに出力します。同様に、OptiFDTDでもFDTD法での解析結果をテキストファイルに出力することができます。両ソフトウェアとも入射光をデータファイルで指定できるので、この機能を利用してデータの受け渡しを行ないます。(図1)(3) 連携解析の基本的流れ
ここでは、図1のモデルを例にOptiBPMとOptiFDTDによる連携解析(2D)の基本的な流れをご紹介します。まず、OptiBPMにて(1)の直線導波路モデル作成し、光を伝搬させます。その際、モデル終端での複素振幅フィールドデータをファイルに出力するように指定しておきます。
次に、OptiFDTDにて(2)の90°反射モデルを作成し、入射光として(1)で出力したデータファイルを読み込み、伝搬の様子をシミュレーションします。ここでも伝搬後のデータを(3)へ渡すために、OptiFDTD_Analyzerにて反射後の複素振幅フィールドデータをファイルに出力しておきます。
最後に、OptiBPMにて(3)の直線導波路モデル作成し、入射光として(2)で出力したデータファイルを読み込んで伝搬シミュレーションを行います。
シミュレーションの結果を確認すると、(2)にて反射した光が導波路の中心からずれているため、(3)の直線導波路部分では光がうねりながら伝搬している様子が確認できます。
この結果から、ミラー位置などの調整が必要なことが分かります。
(4) 損失の計算
全体でどの程度の損失があるかを計算するために、まず(1)(2)(3)の各部分での損失を計算します。まず始めに、(1)の始端でのパワーと終端でのパワーを元に(1)の部分での損失を求めます。
この例では、シングルモードの直線導波路にその基本モードを入力する設定としているため、損失はほぼ0となっています(図2)。
次に、(2)での損失を求めます。
OptiFDTDでは、Crosscut Viewerを使って始端(面AB)でのパワーと終端(面BC)でのパワーを確認できます(図3)。
最後に、(1)と同様の方法で(3)での損失を求め、これらの結果を基に(1)(2)(3)全体での損失を求めることになります。
全体での損失の計算は以下のようになります。
(1)の始端からパワーが1の光を入射したと仮定すると(1)の終端で0.002%損失して0.99998になり、その光が(2)にて約8.3%損失し、0.917になり、そしてその光が(3)に入って約6.558%損失し0.857になります。よって、全体での損失は約14.3%になると見積もることができます。
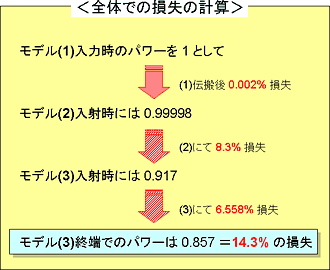
図5 全体での損失
連携解析による利点(1)― 解析時間の大幅な短縮
今回のような連携解析の大きな利点の一つとして、解析に掛かる時間を大幅に短縮できるということが上げられます。FDTD法で直線部分(1000μm)を解析することを考えた場合、多大な時間が掛かるだけでなく、メモリの上限により計算自体が行えないことも予想されます。下図は(3)のモデルの100um(1/10)までをOptiFDTDで解析した結果とOptiBPMで解析した結果です。OptiFDTDだと、この100umの解析に30分ほど掛かりますが、OptiBPMだとたった数秒でFDTD法での結果と同等の精度で解析できます(使用PCスペックはCPU 2.2GBメモリ1GB)。(図6)
連携解析による利点(2) ― 精度の向上
2つ目の利点として、解析精度の向上が上げられます。BPM法ではその手法上、伝搬軸に対して垂直に伝搬する光や、戻ってくる光を解析することはできません。また伝搬軸に対して90°以内の伝搬であっても、その角度の大きさに比例して精度が劣化します。今回、反射の部分をBPM法にて解析するために、導波路の直線部分を伝搬軸に対して45°傾けて90°反射のモデルを作成していますが、これを最高精度の広角アルゴリズム(Pade(4,4))を用いて解析したとしても精度が劣化してしまうことが予想されます。
これに対し、FDTD法には角度の制限が無いため、どのような方向に伝搬する光に対しても精度よく解析することができます。
図7に90°反射の部分をOptiBPMにて解析した結果とOptiFDTDにて解析した結果を示します。 BPM法での解析結果(図左)とFDTD法で解析した結果(図右)を比べると、BPM法による解析の方があきらかに反射部分での放射が多くなっていることが確認できます。
(6) おわりに
以上のように、両ソフトウェアを連携して使うことで、BPM法だけでは解析が困難な90°反射のモデルも精度良く解析でき、かつ、非常に短時間で解析することができます。*連携解析の際の注意点などはこちらをご参照下さい。
詳細な操作方法につきましては、それぞれのソフトウェアのマニュアルをご参照下さい。
また、OptiBPMは、光システム全体の特性をシミュレーションする OptiSystem や、レンズ設計の分野で広く使用されているCODE VやZemaxとの連携機能も持っており、これらのソフトウェアを組み合わせることで、更に幅広い範囲にシミュレーションを適用することが可能になります。